日本再発見塾
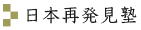
日本再発見塾
| 最上町について | 講師陣 | タイムテーブル |
| 当日の様子 1日目 | 当日の様子 2日目 | 参加者の感想 |
| 報告書(PDF/7.13MB) | ||
◇
早朝プログラム:香道体験 場所:逍園

蜂谷宗 師範に志野流香道のお稽古をしていただきました。 香道とは、作法に基づいて香木をたき、その香りを鑑賞して楽しむ、茶道・華道と並び日本を代表する伝統芸能です。初めて体験する方が多い中、心地よい緊張感と開放感を得るひとときとなり、香道の奥深い世界を垣間見ることができました。
師範に志野流香道のお稽古をしていただきました。 香道とは、作法に基づいて香木をたき、その香りを鑑賞して楽しむ、茶道・華道と並び日本を代表する伝統芸能です。初めて体験する方が多い中、心地よい緊張感と開放感を得るひとときとなり、香道の奥深い世界を垣間見ることができました。
◇
早朝プログラム:収穫体験 場所:阿部範夫さんの畑

アスパラガスやトマトなどの農作物を収穫させていただきました。
アスパラガスの収穫風景 朝もやにつつまれてとても幻想的です。
◇
早朝プログラム:朝市

河原沿いに開かれた朝市の様子。旬のとてたての野菜やお漬けもの、郷土料理等、特産品がずらり並びます。試食をした人から「とても美味しい!!」と感動の声が。楽しい交流がありました。
◇
宮原ゼミより “子育て支援温泉 ”発表

宮城大学事業構想学部の宮原ゼミは平成18年より赤倉温泉で、地域振興、観光振興を通じた地域活性化の活動に取り組んでいます。子連れで温泉に来れる「子育て支援温泉」をコンセプトに、住んで楽しい、訪れる人たちが気軽に地域と交流でき、子育てする人がほっと一息つける包容力のある温泉地づくりの提案をしています。
◇
第四部 歌垣復興
「歌・俳句ではじめる新コミュニケーション」

昨年、飯舘村で好評だった歌垣を、最上町で再現することとなりました。歌垣とは万葉の時代に、あえて顔や名は明かさずに男女が山野に集い、互いに短歌や俳句を詠みあって掛け合うことで、思いを伝える恋の駆け引きのことです。この歌垣がきっかけで、現実に見事カップルになった昨年の師範山村レイコさんより幸せいっぱいの応援メッセージが届きました。
師範は昨年に引き続き、俳人の黛まどかさんと国文学者の上野誠さん。作曲家の千住明さん、スポーツジャーナリストの増田明美さん、脳科学者の茂木健一郎さんも駆けつけて下さり、豪華な顔ぶれが揃いました。歌垣は次のようなプロセスで進められました。
・参加者に問歌・問句がそれぞれ事前に3つずつ伝えられ、参加者が好みのものを選んで答歌・答句を返します。
・応募作品の中から、黛師範と上野師範が下記の3首・句を選びます。
・それぞれの答歌・答句の詠み人を明かさない状態で、問歌・問句の詠者が最終的に一首・句を選びます。結果は次のようになりました。お名前のあるのが最終的に選ばれた作品です。

秋の夜の湯屋に集いし旅人が月に照らされ夢を語らん
(高橋 最上町長)
・秋の夜の湯屋に集いしきみとわれつきに照らされ愛を語らん
・月が聞く湯屋の集いの笑い声小国の川に夢の輝く(宮原育子さん)
・旅人もやがては日々に還りゆく一夜限りの宿のあかりよ
減反のきびしさ耐えて今日も又農外作業に老の汗ふく
(大場善男さん 第1区区長、ボランティアガイド)
・君がため農政変えんと汗流す遠くにありとも常に忘れじ
・精悍なあなたの横顔惚れ惚れとそばに寄り添い稲穂渡すよ
・ひとつぶに祖先のみこころ受けとめし感謝しつなぐ明日への命(市原優子さん)
・老の汗転作図ってアスパラに明日の最上の夢ふくらむ(努力賞:齋藤知事)
小さき手をそっと開きて放流の稚鮎見守る子らの目清き
(笠原さよ子さん地元小学校養護教諭)
・放流の稚鮎見詰めし清き目の少し濁りて試験に臨む
・あたたかいやさしい場からの旅立ちを見送るまなざしこころ豊かに
・疑ひの心知らざる幼子のその眼に映す水は澄みゆく(堤亜由美さん)
すすき道影をひとつに二人かな
(増田明美 スポーツジャーナリスト)
・その影のなかよく揺れて月今宵(小林義和さん)
・すすき道微かに見える後ろ影
・君想う心は揺れしすすきかな

露草や愛といふ字を書いてみる
(北村昭夫さん)
・気まぐれな愛かも知れず猫じゃらし
・愛という字は何処にや野分後(阿比留聰子さん)
・まどか素敵清水そのままにまどか最高
別々に来て澄む水に落ち合へる
(黛まどか 俳人)
・逢えぬ日の涙あつめて秋の水
・水に月耳を澄まして君を聴く
・再会にはずむ心や水の秋(高家章子さん)
発表の後、茂木健一郎氏が感想を求められ、「どきどきしたりワクワクしたりすることを忘れると脳は年をとります。歌垣は好きな人を益々好きになる効果があるかもしれません。」と述べられました。再発見塾の「疑似」歌垣でもこんなに盛り上がるのですから、確かに、現代にあっても男女間のコミュニケーションのツールとして効果が期待できるかもしれませんね。
◇
大黒舞披露

第四部の締めくくりには、立小路大黒舞保存会による大黒舞の披露がありました。
収穫の喜びを表す、華やかで力強く軽快な踊りの披露でした。
◇
昼食

河原で最上の芋煮をいただきました。
◇
第五部 まじゃれ放談会

司会:加藤秀樹
二日間の総まとめとして、各グループ代表者からの活動報告をした上で、数名の師範や達人の方々からの感想を聞きました。
師範のコメント
●増田明美師範:
地元の方々が地元の言葉で説明してくださっているのを聞いて、とても爽やかな気持ちになりました。
●千住明師範:
分水嶺に行ってきましたが、水の流れは驚くほど自然でした。彫刻家の巨匠であるイサム・ノグチが、自然の営みには到底敵わないと言っていたが、まさしくこれを感じました。現在のJ ポップは“扇風機の風”のようであり、自分は“そよ風の音楽”を作って いきたいと思いました。
●茂木健一郎師範:
最近の日本人は、質感を通じて良さを感じる、ということが出来なくなってきていると思います。高尾山がミシュランガイドに三ツ星をもらった後、大人気になったという話だが、外国人にその良さを教えてもらわなければいけなくなっているというのがいい例。また、日本では、人間が手を加えて余計なことをしなかったから、未だに良さが残っているというところが多い。そうではなく、良さを感じて、最上のような良いところが残っていけるようにしなければならないと思います。

●麻殖生素子師範:
「ハ」グループに参加しましたが、人間の作った道路を通って村まで降りてきたハクビシンに、合鴨が食べられてしまったという話など、簡単なことではないということを実感しました。また、松林寺に泊まったことで、お寺との距離を近く感じるようになりました。困ったときに英知を貰いながら生きて行けるところだと思いました。すばらしい土地で生きていることを誇りに思ってほしいです。
●坂本廣子師範:
宿舎のご協力を得て、昨日の夕食の料理は、山里で採れるもののみを使って料理しました。
●蜂谷宗 師範:
師範:
「ロ」グループに参加し、日本を代表する伝統文化の家元に生まれたとはどういうことかを考えました。
●藤原誠太師範:
松林寺でミツバチを飼ってくれることになり、大変嬉しく思います。
●三部義道達人:
林間学校のようで楽しい経験でした。起床したときの女性の顔が子供のようで爽やかでした。
◇
閉講式

黛まどか呼びかけ人代表が「このようなイベントを開催するとなれば通常、イベント企画会社やプロデューサーが出てきて、膨大なお金をかけ、様々なものが持ち込まれ機械的に運営されます。日本再発見塾の良さは、進行の拙さもあったかも知れませんが、お金をなるべくかけずに時間をかけ、地元の人が知恵を絞って地域にあるものを利用した、気持ちの込もった手作りのイベントだということです。だからこそ地元の人や参加する私達にたくさんの発見や気付きを与えてくれるのだと思います」とのまとめのあいさつをし、地元達人・実行委員会たちがそれぞれお礼のあいさつをしました。これからもこの活動を最上町で継続していきたいと決意を新たにしました。


