日本再発見塾
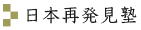
日本再発見塾
爽やかな青空とほのかに色づき始めた奥羽山脈の山々、秋の収穫を迎えた山形県最上町で「第四回日本再発見塾in 最上」は始まりました。
| 最上町について | 講師陣 | タイムテーブル |
| 当日の様子 1日目 | 当日の様子 2日目 | 参加者の感想 |
| 報告書(PDF/7.13MB) | ||
◇
最上町について
最上町は、山形県の右上、秋田県と宮城県に接する人口約10.000 人の町です。北と南に1000mを越える山々が連なる奥羽山脈に囲まれた盆地に位置し、分水嶺があります。分水嶺のある集落としては全国で二番目に低い海抜338m となっています。
主な産業は、諸国行脚の旅にあった慈覚大師(円仁)よって863 年に発見されたという伝説のある1100年余りの伝統を持つ温泉です。東北一の湯量を誇り、赤倉温泉として親しまれ、現在は日帰り入浴用の「湯めぐり手形」を発行し、県をまたぎ鳴子温泉等近隣の地域でも使用ができるようになっています。また、冬季はスキー、夏季は高原での自然体験が観光の目玉で、2003年に「100 万人交流促進条例」を制定し、交流人口拡大に力を入れています。
町のあちこちに湧き出す清水は、稲作や岩魚の養殖に利用される他、人々は炊事から洗濯まで生活全般に利用しています。ペットボトルの水を買う人は稀な程です。町民のアイデアを活かし、アスパラガスやヤーコンの栽培、米粉パンの開発など、町独自の取り組みも積極的に実施しています。
赤倉温泉郷の真ん中を貫いて流れるのが一級河川の小国川です。松原アユと呼ばれる天然鮎が釣れる川として全国的に知られている他、小国川沿いに続く赤倉渓谷では、新緑や紅葉、雪化粧した山々など四季折々の変化に富んだ自然を満喫することができます。そして周辺には、松尾芭蕉が「おくのほそ道」で2 日間逗留した「封人の家」や、太さ日本一の大アカマツ、国内でも類を見ない大きさを誇るカツラの木など、旧跡や名所が多く遺されています。奥羽山脈から流れ来る出来たての水を中心に、自然と支え合いながら生きる日本人の姿が現存する町です。
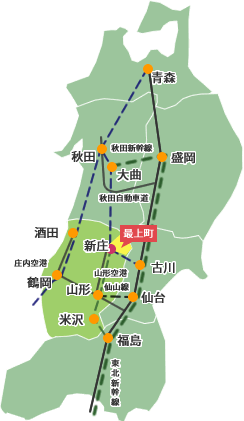
「最上」〜清水(すず)とつながってみる、2日間〜


地元から、都会から、いっぱいの好奇心を抱えて集まってきた多彩な講師陣と参加者たちが、共に学び、共に遊び「日本文化とその原点である地方を元気にしよう」と思いをひとつにする日本再発見塾。
四回目の開催地は、できたての水、できたての空気のある山形県最上町。奥羽山脈の分水嶺に位置し、最上町に湧き出た水は太平洋と日本海へと流れていきます。水を大切にしてきた人たちの生活や知恵を学び、体験する2日間です。
●主催:第四回日本再発見塾実行委員会
●協賛:アサヒビール株式会社
株式会社アスク/株式会社空
株式会社大伸社/高畠ワイン株式会社
株式会社早坂建具製作所
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社ヨコタ東北
●協力:アディダス ジャパン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
環境goo(NTTレゾナント株式会社)
●後援:構想日本/サカモトキッチンスタジオ
東京財団/湯治舎/山形県
◇
師範
| 俳人 | :黛 まどか |
| 万葉学者 | :上野 誠 |
| 料理研究家 | :坂本 廣子 |
| 作家 | :塩野 米松 |
| 作曲家 | :千住 明 |
| 志野流香道家元後嗣 | :蜂谷 宗 |
| 養蜂家 | :藤原 誠太 |
| 表装作家 | :麻殖生素子 |
| スポーツジャーナリスト | :増田 明美 |
| 宮城大学事業構想学部教授 | :宮原 育子 |
| 脳科学者 | :茂木健一郎 |
地元達人の方々
| あべ旅館 女将 | :阿部 邦子 |
| 居酒屋・蛍 女将 | :五十嵐 京子 |
| 山刀伐峠ボランティアガイド | :大場 善男 |
| あい鴨農法 | :奥山 勝明 |
| 米工房組合 理事長 | :栗田 靖子 |
| 松林寺 住職 | :三部 義道 |
| 緑を愛する会 会長 | :柴崎 喜美男 |
| 釣り名人 | :高橋 忠義 |
| クラブ食堂 経営 | :田中 綾子 |
| 米農家・岩魚養殖 | :西塚 幹夫 |
| マタギ | :本間 山田 |
| ペンキ・塗装職人 | :山田 公美 |
◇
「日本再発見塾 in 最上」タイムテーブル
1日目:平成20年10月4日(土)
12:00 |
受付開始 |
12:15 |
開講式 |
12:45 |
昼食 |
13:20 | 14:50 |
第一部:日本人と水は昔、とても親しかった 「地元のお年寄りが語る、水と暮らしの変化」 聞き手:塩野米松師範 達人:岸亨、田中綾子、本間山田、山田公美 美しい水の村に暮らしていた日本人は、どう水に親しんでいたのか。 地元のお年寄りから、水と暮らしの変化についてお話を伺いました。 |
15:00 | 17:00 |
第二部:フィールドワーク「清水(すず)の道探し」 |
| イ「水と植物・生物」(前原高原) 師範:塩野米松 達人:西塚幹夫 水源や田んぼ、岩魚の養殖場に伺いました。 水と植物や生物の関係や、水の循環について学びました。 |
|
| ロ「水と文化」(赤倉温泉・あべ旅館) 師範:上野誠・蜂谷宗  達人:阿部邦子 達人:阿部邦子「奥の細道」の全文が書かれたお茶室で、水にまつわる文化である茶道を体験しました。 |
|
| ハ「水と農業」(立小路) 師範:藤原誠太・麻殖生素子 達人:奥山勝明 三部義道 アイガモ農法を実践されている奥山さんの田んぼに伺いました。 古い農具を見せていただき、稲刈りを体験して農業における水の重要性を認識しました。 |
|
| ニ「川と漁」(赤倉温泉・小国川) 師範:宮原育子 達人:高橋忠義 小国川でカジカ釣りを体験しました。 川の恵みを実感し、水を守る大切さを学びました。 |
|
| ホ「森と炭焼き」(堺田)
師範:澁澤寿一 達人:本間山田・柴崎喜美男 炭焼き窯に伺い、炭作りの最初の段階である伐採から、完成した炭を窯から出す窯出しを 体験しました。美しい水を守るためには、保水の役割を持つ森を守ることが不可欠であると 学びました。 |
|
| ヘ「最上の郷土料理」(赤倉温泉) 師範:坂本廣子 達人:五十嵐京子 最上の食材を使って、最上ならではの郷土料理を作りました。 米やそばなど、おいしい水からおいしい作物が生まれることを実感しました。 |
|
| ト「山刀伐峠と芭蕉」(山刀伐峠) 師範:黛まどか 達人:大場善男 芭蕉が「奥の細道」で通ったという山刀伐峠をたどり、季節の変化を肌で感じました。 俳句を詠み、芭蕉の気持ちに思いを馳せました。 |
|
| 第三部:学生気分で語り合う夜「大人の修学旅行」 | |
18:30 |
夕食 各自宿泊先で、最上の郷土料理を中心とした夕食を頂きました。 |
20:00 |
交流会 フィールドワーク毎に分かれて、師範や地元達人を交え、第二部で感じたことを語り合いました。 |
22:00 |
就寝 |
2日目:平成20年10月5日(日)
6:30 |
香道: 逍園にて、蜂谷師範と香道を楽しみました。 収穫体験: 阿部範夫さんの畑で、農作物の収穫をさせていただきました。 朝市: 赤倉温泉で開かれる朝市に訪れ、最上の特産物や地元の方との交流を楽しみました。 (希望者のみ) |
8:00 |
起床・朝食 |
9:00 |
お湯トピアに集合 |
9:15 |
宮原ゼミ・まちづくり協議会より、“子育て応援”発表 |
9:25 |
千住明さん・増田明美さん・茂木健一郎さんより、ご挨拶 |
9:30 |
最上町音頭保存会 |
9:40 | 11:00 |
第四部 「歌・俳句で始める新コミュニケーション」 師範:黛まどか・上野誠 昨年好評だった歌垣を、再び行いました。 上野先生に歌垣についてお話を伺い、古人の心に思いを馳せた後は、愛の句・歌の作者が、寄せられた答句・答歌の中から、心の通った作品を選びます。 |
11:00 |
大黒舞披露 地元の方に、収穫の喜びを表す大黒舞を披露していただきました。 |
11:20 |
昼食 芋煮会 河原で、地元のお母さん方が中心となって作ってくださった、芋煮やお惣菜を頂きました。 |
13:00 | 14:30 |
第五部 「まじゃれ放談会」 フィールドワーク各グループの代表者に、第二部の報告をしていただきました。 師範や達人とともに、二日間の学びを振り返りました。 |
14:30 |
閉講式 |
15:00 |
解散 〜 仙台駅へ向かう道中、堺田古民家の直売所に立ち寄りました。 |


