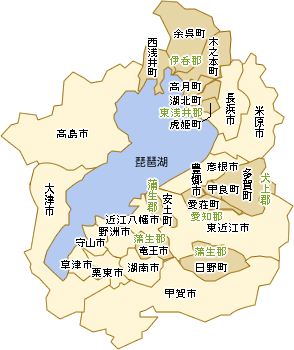日本再発見塾
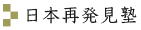
高島アラカルト
「水と緑 人の行きかう 高島市」 とは・・?| 高島市は、滋賀県の北西部に位置し、総面積は約511キロ平方メートル、総人口は約5 万5千人を擁しています。 2005年1月1日にマキノ町・今津町・朽木村・安曇川町・高島町・新旭町が合併し、新しく高島市が誕生しました。気候的には日本海側に近いことから冬季の寒さは厳しく、積雪量の多い日本海型気候となっています。また、秋季には「高島しぐれ」と呼ばれる降雨がしばしばあります。 |
経路探索〜「生水(湧き水)」と「川端(かばた)」のある生活〜
|
| ■高巖山曹洞宗興聖寺 (こうしょうじ) 別名道元禅師開闢道場。元々は城で、かつての福 知山城城主朽木氏の本家(菩薩寺)にあたる。 仁治元年(1240)に七堂伽藍が完成し、以後代々佐々木信綱庶流の朽木家の菩提所として発展し、また永平寺の直末として存続している。室町中期以降には足利将軍の仮御所として使用された。境内には、国の名勝指定を受けている足利庭園がある。 |
 |
| ■正傳寺(しょうでんじ) 高島市には「西近江七福神めぐり」がある。開運招福の宝印を求める人たちの人気となっているが、この正傳寺には古代インドの破壊神で大国主命(おおくにぬしのみこと)と習合して食厨の神となった大黒天が祀られている。山門をくぐった左手に湧き水があり、本尊には平安時代に仏師有円・寛応作の木造薬師如来座像が安置されている。 |
 |
| ■藤樹書院 近世初期の儒学者、中江藤樹・なかえとうじゅ(1608 〜48)が開設し、晩年を過ごした近世最古の私塾。門 弟や村人の発意により土地を買い広め、慶安元年 (1648)に創建される。寛政8年(1796)光格天皇よ り「徳本堂」の堂号を賜わる。明治13年(1880)上小川村の大火で創建時の建物は焼失し、2年後に県内外の募金によって瓦葺の建物として再建される。 |
 |
| ■朽木新本陣 道の駅「くつき新本陣」は昭和62年、鎌倉時代から明治維新までの間、この地を治めた朽木氏の城館・朽木の中心であった朽木本陣の機能を復元し、むらづくりの発信基地、村民のコミュニケーションの拠点として誕生。朽木地域の観光情報発信、コミュニティー醸成特産品の紹介にイベントの開催などバラエティーに富んだ機能を備えている。 |
 |
| ■日曜朝市 正月三が日を除く毎週日曜日と祝日の午前7 時から、地元の人たちが自作の産品を持ち寄る朝市を開催している。新鮮な農作物のほか山菜、漬物などが喜ばれており、中でも一番の人気特産物は「栃餅」と「鯖のなれずし」。栃の木が多いこの地の土地柄と、鯖街道の名残を今に伝える味。朽木の歴史と個性が感じられるふるさと産品として根強い人気がある。 |
 |
| ■栃餅 あんこや蜂密など甘いものに合う栃餅は、少々の酸味と、こくのある独特の味と香りが特徴。そのままでは食べられない栃の実を、木灰と山の清流にさらしてアクを抜き、自家製のもち米と合わせてつきあげる伝統食。 |
 |
| ■鯖のなれずし 朽木の特産品“鯖のなれずし”は平安時代から作られている。背割りした一塩鯖の腹にご飯を詰め込み、山椒と塩を振って桶で発酵させて作る伝統の保存食。血圧を正常に保ち、豊富なビタミンが疲労を回復させ、健康食としても最適。 |
 |
もっと知りたい!朽木!
〜朽木ヒストリー〜朽木が歴史の門戸に顔をのぞかせるのは、おおよそ1000年前。古くは「朽木谷」または同義で「朽木郷」「朽木杣(くつきそま)」と呼ばれてきた。「朽木庄」の呼び名もあるが、平安時代に見える「朽木荘」が荘園名として比較的長い歴史を持つ。
奈良時代、朽木谷から「朽木の杣」、すなわち材木を東大寺の建築用材として筏で搬出した記録が残っている。安曇川からびわ湖を経て、淀川、木津川とわたり、奈良坂を越えて運ばれたもの。
貝原益軒の「諸国めぐり」に、朽木の杣は朽木谷の奥にあり、名所なり云々…とあるように朽木谷一帯は名木の産地として古くから盛名をはせていた。因みに、朽木の名は古事記にある「木神久々能智神」を祭祀した故から生じた「久々」が変化したもので、“樹木繁茂の地”の意があると言う。
しかし、一方で朽木を有名にしたのは戦国期、この地に地頭の朽木氏が室町幕府の十二代将軍義晴、十三代将軍義藤を匿い、政務を補佐した故事によるところも大きい。そのロマンは今も、村内の禅寺等で、垣間見ることができて興味深い。
| 〜朽木の伝統工芸品〜 原料や製法に多少の差異はあっても、昔の名物は今も健在である。食べ物だけでなく、朽木は古くから塗物の椀や盆など、木工品の産地として有名な土地柄だ。豊富な「朽木の杣」、「漆」などを利用してつくられた膳具のことが古書の「毛吹草」や「嬉遊笑覧」に散見できる。 |
 |
高島市の著名人
〜近江聖人 中江藤樹(なかえとうじゅ)〜
|
||||||
高島ゆかりの文学
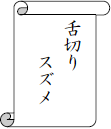 |
〜高島にまつわる民話〜 旧高島町が舞台。竹藪の中にスズメのお宿があった旧高島町から旧安曇川町にかけては竹藪も多く、安曇川流域では豊富な竹を利用して扇の骨(扇骨)が古くから生産されていた。それはいまも変わらず、高島扇骨として全国シェアの約9割を占めている。 |
安曇川周辺の観光案内
■近江聖人中江藤樹記念館中江藤樹は「日本陽明学の祖」といわれている江戸初期の儒学者で、のちに近江聖人と称されている。館内には町の歴史と文化、中江藤樹に関する遺品や資料などが転じされています。※JR安曇川駅から徒歩で10分
■滋賀県立びわ湖こどもの国
琵琶湖畔にある、ネイチャー・ゾーン。「発見の池」「冒険の水路」など自然の中に遊び心をくすぐる施設がズラリ。キャンプ場も整備されており、アウトドアを楽しむことができます。※JR安曇川駅からタクシーで10分
■陽明園
王陽明の生地である中国の余姚市と、中江藤樹の生誕の地である安曇り川町の友好交流のシンボルとして建設された中国式庭園です。※JR安曇川駅から徒歩で12分
※主要参考資料ホームページ※
滋賀県ホームページ: http://www.pref.shiga.jp/
高島市ホームページ: http://www.city.takashima.shiga.jp/
朽木商工会ホームページ: http://www.kutsuki.or.jp/
旧安曇川町商工会ホームページ: http://www.jungle.or.jp/adogawa/touju.html
 このページのトップへ
このページのトップへ